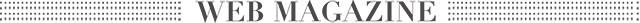白須美紀
【活版クリエイター紹介 vol.1】
古い活字をいかしながら、守り継ぐ
-京都・りてん堂-

京都は洛北の住宅街に、活版印刷でものづくりをする「りてん堂」はある。店主の村田さんは編集プロダクション勤めのグラフィックデザイナーだったが、会社を辞めて2012年の4月に店を立ち上げた。そのきっかけとなったのが、古い活版印刷機「チャンドラー」と店に並ぶたくさんの活字だ。


もともと活字が好きだった村田さんは、家の近所にある活版印刷所の主と親しくなり、工場に出入りをしていた。すると急にその印刷所が廃業することになったのだ。「チャンドラー」と活字は、引き取り手もなく廃棄されるという。「貴重な印刷機と活字を何とか守りたい」と村田さんは貰い手を探してまわったが見つけることができず、ついに自分が引き取るしかないと覚悟を決めた。そして、グラフィックデザイナーとして独立し、かたわらで活版印刷もしていこうと「りてん堂」を立ち上げたのだ。村田さんが印刷所に通い出してからたった4ケ月後の出来事だった。
無我夢中でオープンした「りてん堂」だったが、店頭で「チャンドラー」を動かす村田さんの姿は通りがかりの人々の注目を集め、宣伝をする前から色々なお客様が訪問してくるようになったという。そして、古き良き時代の活字と活版印刷ならではの仕上がりの存在感は人々を惹きつけ、名刺やショップカード、結婚式の案内状、カレンダーなどの注文が入るようになった。仕事の柱はデザイン業だが、年々活版印刷の依頼が増えているという。店頭にはオリジナル作品の豆文やポストカード、ぽち袋なども販売されており、観光客に人気を得ている。


実は活版印刷自体は技術の進歩により、デジタルデータから樹脂版をつくることでさまざまな書体、ロゴマークやイラスト、写真さえも印刷が可能となった。活字を一つ一つ拾って並べていた時代とは隔世の感がある。村田さんの場合、そうした樹脂版による印刷もデザインに取り入れるが、主役はあくまでも手元にある活字だ。書体は今はもう無い「河本精文社」と「モトヤ」の活字のみ。文字の大きさ、空間や配置にミリ単位でこだわり、表現する。
その真骨頂ともいえるのが、2016年春に行った個展「白ヲ読ム、」の作品だ。活字を組んだ版を印刷するとき、活字以外の白場はどうなっているかといえば、何の凹凸のない平らな板を紙のサイズに合わせてパズルのように敷き詰めてあるのだ。空白部分の板をきちんとはめ込まないと印刷するときに版がずれたり、ばらけてしまう。実はこの空白部分の板をはめ込む作業が、かなりの技術を必要とするのだそうだ。
作品を見せてもらっていると、文字の配置と白場だけでさまざまな表現が可能になることがよく分かる。言葉と言葉のあいだに配置された「白」を目で追うと、わずかな時間が生まれ、それが余韻となる。このときわたしたちはまさに白を読んでいるのだ。
作品の中には蝶が飛んでるように組まれたものもあった。とても控えめな表現なのだが、版を組むことを想像すると相当に手間隙がかけられていることが窺える。これも印刷が分かっているからこそできる技で、グラフィックデザイナーと活版印刷職人と活字アーティスト、3つの顔を持つ村田さんならではの作風だといえるだろう。


これらの作品からは、村田さんの活字への想いが伝わってくる。だが「単に活字を印刷したら良いというのではないんです」と、村田さんはいう。「活字を使って良いものをつくることが大事なんです」。
プリンターのようにデータから直接印刷できる機械もある昨今、人が活字を拾う活版の印刷を、文字数の多い新聞や書籍などに使うことはもはや現実的ではない。昔ながらの印刷をそのまま続けていくことは難しいのだ。デザインの力を使い、活字の魅力を新しく見つけて形にしていかねばならない。そうすることでしか、このレトロな活字と印刷スタイルを守っていくことはできないのだ。
村田さんの作品はどれも、一見シンプルで静謐な佇まいをしている。だが、「白ヲ読ム、」の作品を見た着物アーティストの先輩から「もっとエモーショナルな作品も作れ」と言われたと、村田さんは笑った。「今の作品ももちろんステキだけど、そういうのもいいですね。新しい村田さんをもっともっと見てみたいです」。わたしも思わずそう返事をしていた。
限られた文字と余白と紙で、どこまで行けるか。村田さんが自分自身を掘り下げていけばいくほど、もっともっと色々な活字の冒険を見せてくれるに違いない。
グラフィックデザイン工房 りてん堂
村田良平

住 左京区一乗寺里ノ西町95
電 075-202-9701
営 AM10:00〜PM6:00
休 日・祝・不定休
交 叡電一乗寺