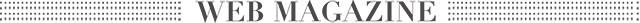白須美紀
美しい仕事から立ち上がる、独自の世界
かみ添
[What A Wonderful Paper World vol.3]

寺院や古い町家を訪れると、襖や壁紙に美しい紋様を見かけるときがある。版木を使って和紙に模様を摺ったもので、「唐紙」と呼ばれる細工紙だ。その名のとおり奈良時代に中国の唐から日本に伝わった技術で、平安時代にはすでに国内でつくられるようになっていたという。はじめは貴族たちが文や歌を書きつける料紙として愛用していたが、やがて襖や壁などの室内を彩る紙へと発展した。時代の変遷とともに、武家や茶人、商家などに愛好されていき、江戸時代には一般に広がったという。
多彩な色柄はもちろんのことだが、唐紙を魅力的にしているのは摺られた紋様じたいの質感と輝きだろう。顔料やそれらを和紙に定着させる布海苔によって、独特の風合いや質感が現れる。雲母(きら)と呼ばれる花崗岩の粉末を混ぜるとなおさらで、細かな粒子が光を受けて柔らかな輝きをみせるのだ。電気のない時代、陰影ある室内に飾られた紋様がかすかなろうそくの灯りや外からの陽光でふんわりと輝きをおびる様子は、何ともいえない美しさだったに違いない。そしていまの時代においてもその魅力は、人々の心を捉え続けている。京都には江戸時代の版木を使い昔ながらの手法で唐紙をつくる工房がいくつも残されおり、文化財の復刻はもちろんのこと、現代建築のしつらいにも使われているのだ。
そんな伝統ある世界で修行し、唐紙の技法で独自の世界を切り開いているのが「かみ添」の嘉戸浩さんだ。職人になる前は、海外でグラフィックデザイナーをしていたという。京都の芸術短大でプロダクトデザインを学んだ後、アメリカに留学。英語を習得した後に、さらに現地の大学に編入してグラフィックデザインを学んだ。
「コンセプトづくりから、タイポグラフィ、印刷まで一通りを学びましたね。ちょうどiMacが登場して、パソコンが一人一台持てて自分でモニター上でデザインができるようになった頃です」
憧れだった海外でデザインを学ぶなかで、嘉戸さんが向き合うことになったのは意外なことに日本のデザインだった。浮世絵の北斎や、彫刻やインテリアデザインで知られるイサムノグチなど、授業のなかで教授たちは口々に日本のデザインを取り上げた。嘉戸さん自身も大学で作品をつくるなかで否応無く「日本人である自分」と向き合うことになり、日本のものに興味が移っていったという。そして留学して3年経った頃、一時帰国した京都で出会ったのが唐紙だった。友人が「好きそうなものがあるよ」と、工房見学に誘ってくれたのだ。それは、後に嘉戸さんがお世話になる修行先だった。
「当時、京都という土地でこれから評価されることをやりたいと考えていたんです。唐紙なら今までのグラフィックの経験が活かせますし、『これだ!』と思いました」
と嘉戸さんは言う。アメリカの大学を卒業しデザインの仕事を始め、日本に帰国してその唐紙工房を再び訪れると企画デザインのスタッフを募集していたというから、なんとも運命的だ。
「デザインの仕事で入ったのですが、摺りも学びました。定時の仕事が終わると『これ刷ってみ』と版木を渡されて、あとはひたすら自分で考えながら摺るんです」
そして職人として仕事ができるようになったころ、嘉戸さんは京都市内の古い町家に出会う。それは将来構えたいと思い描いていた店舗兼仕事場に相応しい物件だった。まだまだ学ぶべきことはあると思っていたが、この建物が独立への背中を押した。以前から版木は唐紙の伝統文様ではなく、すべてオリジナルでいくことを心に決めていた。自分でデザインをして職人に彫ってもらうのだ。伝統の技術で現代のものをつくっていく。グラフィックデザイナーをしていた嘉戸さんだからこそできた決断だった。
制作に必要なのは、模様が彫られた版木と、着色顔料(酸化鉄)や胡粉、雲母などの顔料と、それらを紙に接着させる布海苔、そして篩(ふるい)だ。篩は木枠にガーゼを貼ったもので、顔料と布海苔を合わせたものを篩の布に移し、軽く版木に押し付けて色を載せる。それから版木の上に和紙を置き、道具を使わず手でそっと撫でつけて摺っていく。
版木も和紙もどこかの職人の仕事によるもので、一つ一つが個性を持っており、それぞれ違う。道具や材料との付き合い方、それぞれの相性は、作業しながら加減が分かってくるのだそうだ。その日の天候や湿度によって版木を湿らせる水分や布海苔の濃度も変えていかねばならないし、自分の体調も影響する。まさに職人仕事だ。
「一見作業はシンプルに見えるのですが、実は奥が深い。パソコンを使って文様をデザインするのも、道具を使って作業するのも、手で摺るのも、どれも楽しくてしょうがないんです。そろそろ10年になりますが、全く飽きません」
と嘉戸さんは実に楽しそうに話してくれた。
「かみ添」は襖紙などインテリアのオーダーが中心だが、店にはカードや封筒、ポチ袋などの小物が並んでおり、購入することができる。印象的なのはさまざまな白の姿だった。あたたかく、やわらかく、黄みがかっていたり、青みがかかっていたりする白が、和紙の上に楚々と、きらきらと、しんしんと摺られていた。
「線とか円とかのシンプルなデザインが好きなんです。和紙も顔料も布海苔もすべて自然のものでできていますから、そのなかに幾何学的なものが少し入ると、ちょっとだけ人間が手を加えた感じが出るように思えるんですよ」
ミニマムでシンプルなデザインが中心なのに、何故かとても豊かに感じるのは、そうした素材の力と嘉戸さんの仕事によるものなのだろう。
それを確信したのは、二階の工房にお邪魔して作業を拝見したときだった。壁には摺った和紙を裏張りした跡が無数に残されているのだが、その跡が驚くほど美しい。そこには折り目正しく繊細な仕事ぶりが現れていた。きっと「普通のことですよ」と嘉戸さんは笑うだろう。けれど、たとえ同じ版木と顔料を使って同じ作業をしても、誰もが同じものをつくれるわけではない。嘉戸さんがこんなに美しく繊細に仕事する人だからこそ、「かみ添」の世界は立ち現れるのだ。
そんな嘉戸さんの活躍は、多岐にわたる。2018年には武蔵野美術大学の研究に協力。通称「光悦謡本」呼ばれる慶長期(1596-1615)に刊行された嵯峨本の復元に携わった。当時の職人たちの仕事ぶりをつぶさに辿りものづくりするなかで、「唐紙」の技術が当時よりずいぶん進化していることを実感したという。また、毎年京都で行われる日仏合同アートフェスティバルの「ニュイブランシュ」では、パリでドミノペーパーを制作しているアントワネットポワソンと共作して18世紀の文様から版木を起こし、新たな唐紙を制作した。
「同じ壁紙でもドミノペーパーは金属板でローラーに絵の具を載せてこすります。文様をきちんと出すために素材をしっかりコントロールする作り方なんです。唐紙は手で摺りますし、そこにうまれる絵の具のゆらぎを摺り味として大事にする。西洋と日本の違いが実感できて興味深かったですよ。それに、壁紙を貼るときも西洋は上から下へと貼っていくんですけど、日本は下から上へ貼っていく。紙が重なる部分が上下逆になるのですが、日本のほうが紙の切り口が下になるので埃がたまらないんですよ。面白いですよね」
洋の東西、古今の時間軸も行き来して、新たな刺激を受けていく。それとともに、「かみ添」の唐紙も変化していくに違いない。この先どんなデザインが生まれ、嘉戸さんの白はどんな表情を見せるようになるのだろうか。例えどんな風に変わっても、「かみ添」の唐紙が手にとった人の心を動かすことだけは変わらないに違いない。