三星インキ株式会社
墨について
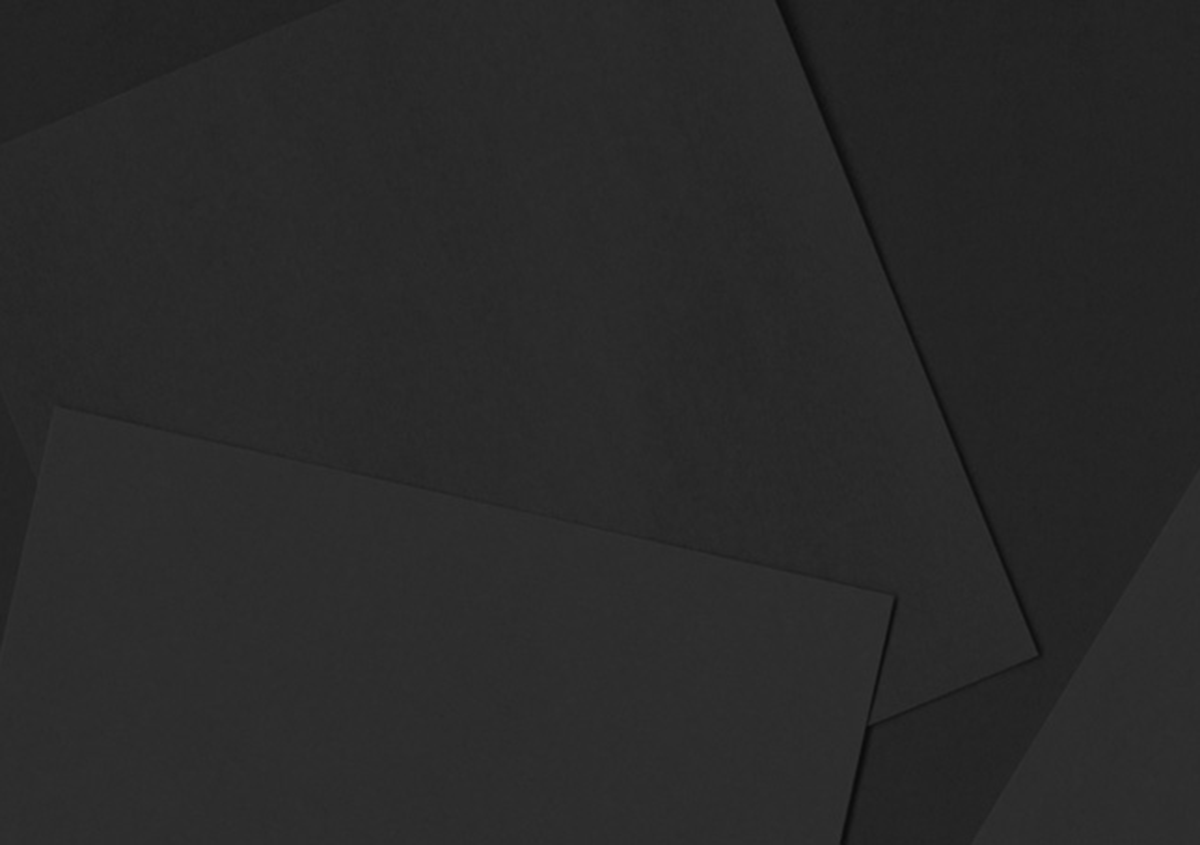
前回、ブリード現象についてお話しさせてもらいましたが、その中で墨インキについて書かせて頂きました。
その際に、なぜ印刷業界では『黒(クロ)インキ』ではなく『墨(スミ)インキ』と呼ばれるのか?という疑問を、当コラムの愛読者の方から聞かれていた事を思い出しました。
我々インキメーカーを含む印刷業界では普通に『墨ベタ』などと呼ぶことがありますが、関わりのない方々からすれば違和感を感じられるかもしれません。
ではなぜ印刷業界では黒(クロ)ではなく墨(スミ)と呼ぶのでしょうか?
墨と聞いて思い出すのが、やはり書道で使用する『墨』だと思います。
この『墨』は煤(すす)と膠(にかわ)を混ぜ合わせて固めたものであり、煤の製造方法は植物油を不完全燃焼させることで発生する炭素の微粒子のことを指します。
そして炭素の微粒子のことを一般的には『カーボンブラック』と呼んでおり、これはまさに印刷インキの色材として使用しています(ただし印刷インキ用のカーボンブラックは植物油ではなく石油系の油を基に製造しています)。
この事から、書道で使用する『墨』と同じ原料(カーボンブラック)を使用したインキであることから『墨インキ』と呼ばれるようになったと考えられます(諸説あり)。
このことから、印刷業界では墨インキと呼ぶのが通例となっております。
以前、当コラムで色についてお話しさせてもらった際、黒(クロ)色というのは太陽光の波長を吸収することで発現する色であります。
それに対して他の色は特定波長の光のみを吸収し、吸収しなかった光を反射させて人の目などに入ることで色と認識されます。
ですので、『カーボンブラック』を色材として使用すれば、本来は真っ黒な色を得ることができるはずなのですが、前回お話しさせて頂いたように、製品によっては『アルカリブルートナー』などの色材を併用使用することがあるのです。
ではなぜこのように補色を行う必要があるのでしょうか?
これは前回お話しした通り、カーボンブラックは真っ黒ではなく、やや黄味の色調を有していることが多いのです。
ということは、カーボンブラックは全ての波長の光を吸収しきれていないということになります。
現在、この世の中に光を100%吸収するものはブラックホールしかないそうで、人の手で作成することができるものとしては『ベンタブラック』と呼ばれるカーボンナノチューブから構成された物質が存在しており、可視光線の99.965%を吸収するそうで、黒さでギネスにも認定されたことがあるそうです。
この『ベンタブラック』のような色材を使用すれば真っ黒な色を得る(光を反射させない)ことはできるのですが、簡単に入手できるものでもないようで、一般的なカーボンブラックを使用する限り、どうしても光の反射が発生してしまうために何らかの色気が発現してしまいます。
この色味を消す方法として、減色混合を利用するという方法があります。
この減色混合については、以前当コラムで書かせてもらいましたが、色というのは多くの色が混ざることで色が消失する(=黒くなる)という特性を有しており、特に黄系統・赤系統・青系統の3つの色が混ざることで色の消失が起こりやすいのです。
このことから、やや黄みを有するカーボンブラックを使用するインキを更に黒くするためには、赤系統と青系統の色を混ぜてやれば良いことから、アルカリブルートナーなどの赤味・青味を有する色材を併用使用する方法が挙げられ、実際にカーボンブラック単体で製造されたインキよりも補色した方が濃度感があるように見えます。
そして補色の種類や使用量などによって、同じ墨インキでもメーカーやシリーズによって黒色感や色調が変わってきます(青口・赤口などという名称が使われています)。
話しは大きく逸れましたが、色々と考えた結果、『黒(クロ)』とは光の反射がない(色がない)状態のことを指すのに対して、『墨(スミ)』は紙などに黒い色を付けることで黒い色を再現することを指すのだと思います。
これは元々書道で使われてきた『墨』の使用目的と同じ、『人に見せる(意匠性を持たせる)』という考え方に繋がるものだと思います。この印刷物を人に見てもらうという気持ちを忘れないためにも、印刷に関連する業界では今後も『墨(スミ)』という呼び方を受け継いでいく必要があるのかもしれません(最後はかっこよく締めて「(スミ)墨マセン」)。
次回も印刷業界を中心としたところでのみ使われる色の呼称について検討していきます。

