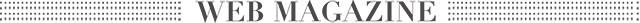白須美紀
【活版クリエイター紹介 vol.10】
「お急ぎは十分」の頼れる名刺屋さん
十分屋

地元でおなじみの活版印刷店
京都屈指の繁華街である河原町通から二条通を東に入ると、街の雰囲気が変わる。大きなビルが姿を消し、昔ながらの町家が点在しはじめるのだ。建ち並ぶお店も、筆や墨などを扱う専門店や仏教経典の書店、品のいいアンティークショップなど、どこかしら歴史や文化の香りがただよう。
そんな通りにあり、懐かしい昭和の佇まいを見せているのが十分屋だ。ショーウインドウには、大きな「お急ぎは十分」の文字。店内には1960年製のハイデル社プラテンT型印刷機が鎮座し、奥には活字がずらりと並んでいる。活版印刷で名刺をつくることができる店として、また特急で対応してくれる店としても、地元京都ではよく知られている存在だ。
3代目店主である山口昌昭さんによると、この場所での営業は58年になるが、店の歴史はさらに古いという。
「太平洋戦争の空襲で大阪を焼け出された祖父が、戦後すぐに疎開先の京都で印刷屋を始めたんです。当時は物資不足で紙も貴重品でしたから確保が難しくて。それで用紙が小さくてすむ名刺に特化したんですよ」
そして独自の特色を出そうと考案したのが「注文から十分で名刺を刷る」という特急サービスだったという。開店当時、店は高瀬川沿いの木屋町通にあり、機械はテキンと呼ばれる小さな手動の活版印刷機だった。活字が足りない場合は、二人の息子たち、つまりまだ少年だった山口さんのお父さんとおじさんが自転車で活字屋まで買いに走ったという。このおじいさんのアイデアは、ファストフード、ファストファッションが当たり前となった現代をうんと先取りしたようなもので、当然ながら京都の人々にずいぶんと重宝された。
そして商売を手伝っていた長男が店を継ぎ、さらに長男の息子である昌昭さんが継いで、今年で店は73年目を迎えた。ハガキや千社札なども請け負うが、やはり看板商品は名刺だ。
「駆け込みでこられるお客様は今も多いですよ。商用や展示会などで京都に来られたのに名刺が足りなくなってしまい『すぐ欲しい』と来店されるんです。それにうちの昔からの常連さんにとって名刺は、“すぐ持って帰って当たり前”なんですよ。パンやお菓子を買うような感じなんです」
と、山口さんは笑う。名刺をつくるのが、パンやお菓子を買うのと同じ感覚になるなんて。そんな風にお客様の生活の一部になっているというのが、街の印刷屋さんらしくてとても素敵だ。





受け継いだ技術と、新しい工夫と
そんな歴史ある十分屋だが、3代目になって変化したことがある。それはパソコンで名刺を製作するようになったことだ。印刷技術の進化によって需要が減ってしまったため活字メーカーの廃業が続いているが、十分屋が使う活字会社も時代の流れに勝てず廃業してしまった。そのため活字の補充ができず、版を組めないケースが出てきているのだ。活字が無い場合は版を組むのではなく、1枚物の亜鉛板を外注することになる。だがそうなると、十分屋の看板である特急仕事は不可能になってしまう。そこで、お急ぎのお客様にはパソコンで名刺を製作し、店内でプリントするサービスを行うようになったという。
もちろん活字があればその場で組んで印刷も可能だ。植字台の前に腰掛けて活字を拾い版を組む山口さんの動きは全く迷いがなく、驚くほどの早さだった。これならば活字を組んで印刷してもらっても「お急ぎは十分」が可能だろう。子どもの頃から家業を手伝っていたベテランならではの見事な技だ。


「父から組版や印刷を教わったことは一度もありません。一緒に働くなかですべて自然に覚えたんですよ」という山口さんだが、仕事が芯から楽しくなったのは、自分の代になってからだという。版の組み方、印刷機の使い方まで、父とはまた違った自分なりの工夫を凝らしているのだ。
名刺の用紙もそんな工夫のひとつにあげられる。活版印刷用に、昔ながらのケント紙や洋紙、和紙などを揃えているが、なかに「鳥の子」という京都らしい和柄の紙があった。白地に白く桜や流水、小菊などが刷られたはんなり優雅な紙で、店一番の高級品だ。この紙だけの依頼ももちろんだが、他の名刺に少量をプラスして刷ってもらうこともできるという。
「季節ものですから、1年通しては使えないんです。桜なら3月中旬から花びらが散る頃くらいまででしょう。夏は流水柄、秋めいてきたら小菊柄といった感じで、季節にあわせて使っていただきたいですね」
着物の柄や和菓子の意匠などと同じで、名刺の季節感にもこだわるのがいかにも京都らしい。また、江戸時代からの貴重な版木で唐紙を手刷りする京都の「唐長」で唐紙の名刺紙を買うと、印刷を頼める店として紹介してくれるのも十分屋だ。実際に、山口さんのもとに唐長ファンや観光客がやってきて、目の前で刷られる名刺に感動するという。




1枚の名刺に美学が宿る
山口さんは活字を組むときは試し刷りも必ず行い、お客様の確認をとる。「ほんの数ミリの違いで印象が変わりますから、文字の配置には細心の注意を払います」といい、名前の上の白場を多めにすると「雰囲気ある名刺」になるのだと教えてくれた。そして、何より大事なことは「シンプルである」ことと、「受け取る人に喜ばれること」だと語った。
「名刺を長く持つことになるのはもらったほうの人ですから、受け取る人に喜ばれるのが良い名刺です。必要最低限の要素だけで、分かりやすく読みやすいことが大切だと思いますね」
使い手だけではなく受け手にまで配慮し尽くした名刺が、すっきりと上品で美しい仕上がりになるのは当然のこと。十分屋が長く京都の人々に愛されるのは、決して早さだけが理由ではないのだ。
ネットで注文すれば安い名刺が簡単便利に手に入る時代、スピードだけでいえば十分屋のライバルはずいぶん増えた。今残されている活字も永遠に使うことはできないだろう。それゆえ山口さんはご自身の息子さんに4代目を継がせたいとは考えていないという。「本人がどうしてもやりたいというのなら別ですけれどね」という山口さんに、それではご自身のこの先はいかがですか、と問いかけてみた。
「お客様が『このおっさんボケてきよったな、勘弁してや』と思われる頃が引退かな。それまでは続けるつもりですよ」
今から27年後、山口さんが84歳のときに十分屋は創業100年を迎える。山口さんのお父さんは88歳の今も現役で店頭に立って仕事をしているというから、不可能な話ではないだろう。山口さんと同世代のハイデルプラテンも、特に手入れしなくても一度も不具合なく快調に動いているというから頼もしい限りだ。
わたしはそっと27年後の十分屋を夢想する。懐かしいドアを開ければ、相変わらずハイデルプラテンと活字があって、昭和の佇まいが残されている。そして、今よりお年を召した山口さんが、変わらない笑顔でにこやかに出迎えてくれるのだ。


十分屋
山口昌昭

住 京都市中京区二条通河原町東入ル
電 075-222-0108
休 日曜・祝日休
交 京阪「三条」駅、地下鉄東西線「市役所前」駅