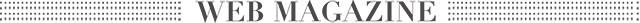森カズオ
徳川家康と活版印刷。

彗星の如き駿河版銅活字
“鳴かぬなら 鳴くまで待とう ほととぎす”
耐えに耐え、天下を手に入れた徳川家康。彼は、その忍耐力とともにすきのない策略によって日本の頂点に立った。合戦上手で、戦略に長け、武人としての印象が強い家康だが、実は文化人としても優れた素養を持っていたのである。
家康は今川義元の人質として8歳から19歳までの12年間を駿府で暮らした。天文18(1549)年から永禄3(1560)年の間である。ただ、人質とはいっても、その待遇は厚く、元服の際は、義元から名の一字を授かり「元信」と名乗った。次いで、「元康」と名を変えたが、やはり一字をもらって(偏諱)いた。また、妻に姪である重臣の娘を与えた。どうやら義元は家康を有力な家臣として育てようとしていたようである。
今川氏の出自は、室町幕府の将軍家である足利家。義元の母は公家である中御門家の娘ということもあり、京の都からは、和歌の名門・冷泉家や蹴鞠の名手・飛鳥井家など当代一流の文化人が数多く拠点の駿府を訪れていた。まさに、駿府は京風公家文化で満たされていたのである。そんな先端の文化にあふれたところで、家康は多感な時代を過ごした。そんな環境の中、家康は今川家の政治・軍事顧問だった禅僧・雪斎に師事する。京都・建仁寺で学んだ雪斎は、印刷事業を行ったことでも知られていて、亡くなる直前の天文23(1554)年には駿府の臨済寺で中国の歴史書『歴代序略』を出版している。家康が14歳の頃である。これが、家康の出版熱をつくりだすきっかけになったのではないかという説がある。
永禄3(1560)年、織田信長が田楽狭間で、上洛を目指して西に向かっていた今川義元軍を襲い、義元を討ち取った。いわゆる「桶狭間の戦い」である。この一件で、晴れて人質生活に終止符を打った家康は、故郷の岡崎城に戻ることになる。以降、家康は信長と同盟を結び、天下統一の一翼を担う。天正10(1582)年に本能寺の変が起こり、信長が明智光秀に討ち取られると、時代は、中国大返しによって光秀を倒した秀吉に白羽の矢を立てる。家康の忍耐の日々は、その後しばらく続くことになる。

話題を印刷に向けてみよう。本能寺の変の8年後、天正18(1590)年、イエズス会によりグーテンベルグによって発明された鉛活字と木製印刷機を用いた活版印刷技術が日本にもたらされた。これについては、以前、『日本人による初めての活版印刷。天正遣欧少年使節団』で詳しく書いている。また、イエズス会などの宣教師たちは、いわゆるキリシタン版と呼ばれる活版印刷物を数多く刷り、布教活動を行っていた。文禄年間(1592~)に行われた朝鮮出兵「文禄の役」の際には、朝鮮から李朝銅活字や刷道具、書籍が持ち帰られ、秀吉から後陽成天皇に献上された。これらを使って、天皇は『古文孝経』の印刷・出版を行ったという。これが文禄勅版といわれるものである。この時代は、ある意味において、我が国の活版印刷の黎明期といえるかもしれない。このような環境の下、家康は何を思っていたのだろう。
慶長3(1598)年、秀吉が亡くなると、家康は石田三成と派遣を争うことになり、慶長5(1600)年に起こった関ヶ原の合戦で、家康は圧倒的な勝利を収め天下を手に入れる。鳴くまで待った結果であった。
この合戦の直前、伏見城に居た家康は、木活字を使って『六韜』や『三略』などの兵書の出版を励行している。いわゆる『伏見版』と呼ばれる出版物である。この時代、豊臣秀頼による木活字による挿絵入り本『帝鑑図説』、上杉家の家老・直江兼続による木活字本『六臣註文選』、京都の豪商・角倉素庵と本阿弥光悦による連綿体の木活字を用いた『伊勢物語』の刊行などが行われ、広い意味での活版印刷がひとつの隆盛を見せることとなる。

駿河版銅活字(印刷博物館所蔵)

「群書治要」(印刷博物館所蔵)
このような活版印刷の置かれた状況の中で、異彩を放つのが家康の動きである。彼は、慶長10(1605)年、息子の秀忠に将軍職を譲ると駿府に移り、大御所として君臨する。そんな中、彼が注力したのは、銅版活字を用いた印刷・出版事業だった。いわゆる“駿河版”である。
“駿河版”の活動は、慶長11(1606)年にはじまる。家康は、伏見円光寺の僧・元佶に銅活字9万余字の鋳造を命じる。この活字を基盤にして慶長20(1615)年から元和2(1616)年にかけて『大蔵一覧集』および『群書治要』が開版された。これは、大坂の陣真っ只中のことである。主に木活字が使われていた時代に、金属製の活字を鋳造させて用いた家康。その製造法は、学者による分析によるとグーテンベルグ以来の西欧の技術と朝鮮からの技術を融合させて生まれたのではないかとされている。既存のものをうまく結びつけ、独自の技術に昇華させる…なんとも日本らしい工夫が施されているようだ。
家康亡き後、金属活字による印刷・出版は急激に衰退していく。まさに、彗星の如く輝き、消えていったのである。そして、活字そのものがつくられなくなり、いわゆる木版という一枚板の印刷・出版が主流となっていく。そして、江戸時代は、さまざまな出版物(仮名草子・人情本・滑稽本・浮世絵など多彩)が世に出て、日本には独特の出版文化が醸成されていく。家康が幼い頃に体験したであろう印刷・出版の存在意義の本質は、確かに受け継がれたのではないだろうか。ただ、彼が興した活字による印刷、つまり活版印刷の復活は、幕末まで待たなければならなかった。ちなみに、家康の命で鋳造された銅活字のうち32,166個は、現存し、重要文化財として印刷博物館で大切に保管されている。

駿河版銅活字(印刷博物館所蔵)

「群書治要」(印刷博物館所蔵)