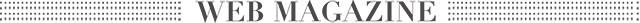白須美紀
和紙の魅力を引き出すデザインの技
WACCA JAPAN

美しい和紙に心ときめく専門店
シンプルでありながら心惹かれる和紙に出会えるWACCA。素敵な紙を探すうちに、イベントやネットショッピングなどでその存在を知った方も多いのではないだろうか。オンラインショップには、選び抜かれた原紙をはじめ、レター用品や文具、紙糸や箸袋にいたるまでさまざまな和紙アイテムが勢揃いする。共通するのは、どれも装飾が削ぎ落とされた、シンプルで美しい品々であるということ。「ああ、和紙とはこんなにも美しいものなのだな……」と改めて気づかされるものばかりだ。
しかも単なる「素敵な和紙のお店」ではないのがWACCAの面白いところだ。商品の大半は、オーナーである森崎真弓さんがデザイナーとして企画デザインし、和紙メーカーと一緒につくりあげたものなのだ。
「わたしはもともとグラフィックデザイナーで、普通にロゴをつくったりパッケージをデザインしたりしていたんですが、15年くらい前からだんだん『日本の伝統文化に関わるようなデザインがしたい』と思うようになったんです。でもわたしが育った郊外の町には独特の文化やお祭りも特にないし、茶道や華道、書道などとも無縁でしたから、何から始めていいか全く手がかりがなくて。唯一仕事柄紙には親しみがあったので、和紙に着目したんです。とはいえまだその頃は『ご祝儀袋やのし紙をデザインしたいな』と考えているくらいで、将来自分で紙を販売するようになるとは思ってもみませんでした」
そして当時の森崎さんはまず、折形(おりがた)礼法の教室へ通いだした。折形礼法とは贈り物や儀式における和紙の包み方、折り方、飾り方のしきたりのことで、鎌倉時代の武家の礼法を起源としており600年以上の歴史があるという。その教室で学ぶなかで、森崎さんはどんどん和紙に魅せられていった。しかし、折形の先生に産地に連れていってもらったり、自分で職人さんのところを訪ねたりして詳しくなればなるほど、和紙の現状にもやもやした思いを抱くようになったという。素材自体は素敵なのに、プロダクトにうまく落とし込めていないものが多いと感じたのだ。
「もちろん中には素敵なものもありましたが当時は今ほど数もなかったですし、和風なものが多くて『もっと広がりがあってもいいのに……』と思いました」
そこで森崎さんは、デザイナーの視点で和紙プロダクトの企画提案する会社を立ち上げる。それが、WACCA だった。まず着手したのが、サンプルづくりだ。
「『和紙の企画をします!』といっても何もない状態だと始まらないので、自分でサンプルをつくりはじめたんです。小ロットで型を抜いてもらったり活版印刷をかけてもらったりとかして便箋や封筒などをつくり、提案ツールとして小さく在庫を持ち始めました」
すると「せっかくあるのだしイベントに出してみませんか?」という話が舞い込むようになり、和紙アイテムを販売することになったという。やがて企画デザインに関わったクライアントのプロダクトも紙のイベントやWACCAのオンラインショップで販売するようになり、現在のスタイルになった。
「今でこそ、デザイン業をやりつつ自分でショップを運営される方も増えていると思うのですが、当時はそういうやり方もノウハウがなくて。オンラインショップも今ほどやりやすくなかったですし、本当に手探りで続けるうちにこういうスタイルになっていました。メーカーさんたちやお客様に育てていただいた結果です」


メーカーと共に和紙の新しい魅力を引き出す
素敵なものが揃うWACCAの商品のなかで、一番の人気は「コピーができる書道半紙」だ。当初は「白」のみの展開だったところ、森崎さんが「バリエーションあった方が絶対売れるからつくりましょう」と提案し、「きなり」が生まれたという。抄紙テストから関わり、きなりのほうはあえて繊維感を出して白と比べるとナチュラルな雰囲気に仕上げたという。
また、緑茶の粉末を抄きこんだ「JAPANESE GREEN TEA PAPER/緑茶抄合」は、美濃和紙メーカーとの雑談のなかから生まれた企画だ。
「ちょうどわたしがデザインの仕事でお茶屋さんと繋がりがあったのでそこにご相談して、茶葉を用意してもらえることになったんです。そして、どんな感じの仕上げにしたらいいか、どれぐらいの配合でどんな見え方の紙にしようか、というのを一緒に考えました。表と裏で抄きこみ具合を変えたのでリバーシブルで楽しめますよ」
さらにいえば、山叶製紙の人気商品「西島和紙 ミニチュア半紙ひとしめ」も実は森崎さんのアイデアだ。
「山叶製紙さんの販売展示のお手伝いをしたときに『ちょっと目玉になるようなものをつくろうよ』と、企画したものなんです。半紙の結び方って地方によってやり方がいろいろあるそうなんですが山叶製紙ではあの結び方で、実際に工場に行くと本物のひとしめが山積みになっているんですよ。包装紙にハンコがたくさん押されてて何だか楽しいですし『あれがミニチュアになったらかわいいよね』と半分遊びみたいな感じでつくったんです」
森崎さんいわく「誰も売れるとは思っていなかった」というミニチュア半紙ひとしめだが、今では出せばすぐに売り切れてしまうヒット商品だ。紙博などのイベントでは中の紙を選んでその場で包んでもらえるため、完売必至の人気ぶりを誇る。そしてイベントではお客さまから「一〆(ひとしめ)」の意味を聞かれることも多く、思わぬ宣伝にもなっているのだそう。
「半紙は2000枚を『一〆(ひとしめ)』とする単位があって全国共通なんですよ。書道と縁のない紙好きさんにも半紙のことを知ってもらえるのが嬉しいですね」
こうしたWACCAの活動によって、森崎さんのグラフィックデザイナーとしての仕事も様変わりしつつあるという。洋のものを和風に落とし込む依頼が増えたうえ、和紙ならではのデザイン発注も増えてきた。
「たとえば洋紙で大きな紙に印刷して後から裁断するのではなく耳付きの原寸を給紙して刷る場合など、和紙はデザインやレイアウトの難易度が高いんです。長年和紙に関わってきて失敗と経験を積めたことでアクロバットな印刷技術みたいなのがわたしのなかで蓄積されて、結構凝ったデザインもできるようになりました」
ときには洋紙しか扱ったことのないデザイナーに相談されて、アドバイスすることもあるのだそう。WACCAを立ち上げるときに産地とよい紙を求めるデザイナーやクリエイターのハブになることも意識していたというが、それが実現した形だ。特別な和紙に印刷するとなるとつい力が入って特殊な印刷を乗せがちだが、そうするとあっというまに予算オーバーになってしまう。和紙自体に存在感があるのだから、削ぎ落として紙そのものが生きるようなデザインをアドバイスするのだそうだ。また予算と効果を鑑みて、結果的には洋紙を使うことに落ち着く場合も多いという。
「目指す完成形を冷静に考えたら『ここは和紙じゃない方がいいよね』となるんです。でも和紙をフックに声をかけていただけるので、ありがたいなあと思っています」


和紙と書の世界を活かし直す
そんな森崎さんがいま注目しているのが「書道」だ。紙だけではなく、モダンな筆ペンや書道具のプロデュースも手掛けている。
「カリグラフィだったり、万年筆やガラスペンだったり、インクだったり。世の中全体でいうと小さなものかもしれませんが、ハンドライティングのブームが結構長く続いています。最近『これは単なるブームではないのかもしれない』と思うようになりました。世の中がデジタル化していく中でやはり『手で書きたい』という人間的な欲求があって、何かしらの形で続いていくんじゃないかなと思うんです」
書道は誰もが小学校で経験するため茶道や華道に比べて敷居は低いはずだが、実際のところは随分縁遠い存在になっている。森崎さんがその事実に気づいたのは、自分で書道をやってみたいと思い立ったときだった。いざ始めてみようと思うと、ちょうどいい道具が手に入らないのだ。
「小学生が使うようなホームセンターや町の文具店にある安価なものか、作家ものなど本格的な高級品、両極しか見つけられないんですよ」
同時期に書道人口の分布グラフを調べる機会があったが、子供から高校生までと、60代以上は書道人口があるのに、20~50代の間は激減。現役世代はほとんど書道に関わっていない、ということも分かった。
「でも20~50代の人たちも、ちょっと素敵な道具とか、気軽に習いに行ける場所みたいなのがあれば、やりたい人はいるはずです。最近はコロナの影響もあって、オンラインで教えてくださる先生も増えてきましたし、『あとは道具だな』と思ったんです」
また、最近ではカリグラフィの分野で墨を使う「和のカリグラフィ」なども出ているそうで、日本人が習ってきた書道だけではない広がりも感じているのだそうだ。
「墨を磨ったときの香りや筆に浸しているときの時間など、書道具が持っている楽しみって実は幅が広いんです。そんな風に楽しめるよう提案を続けたいし、紙の文化も書道そのものもここから広がるといいなと思っています」
そしてもう一つ、森崎さんが着目するのが「和紙のにじみ」だ。
「『この和紙は、にじんだり裏抜けしないので、万年筆やガラスペンに使えますよ』ということをご紹介しはじめてから、売れる和紙がすごく増えました。和紙のハードルが下がってハンドライティングファンの方々に広まっていくのはすごく嬉しいのですが、実は和紙ってそもそもにじむことも良さなんですよ。なので、にじみの面白さを伝えるプロダクトもやりたいと思っているんです」
書道ではにじみも表現の大切な要素であり、書道に関連した販売イベントでは「この紙はにじみません」というとむしろ買ってもらえなかったりするのだという。
「そもそも書道における『にじみ』という言葉は、英語では訳せないそうなんです。『インクが走る』とか『裏抜けする』とかの表現はあるけど、にじむことの美しさを表現する言葉は無いそうです。墨で書くことをしてきたアジアならではの感性なのでしょう。『にじみ』が世界語になるといいですね。それに、もうすでに日本のインクファンのなかには、にじみを楽しむ領域に来られてる方もいるのではないでしょうか」
森崎さんのこうした視点は、表と裏の質感の違いを楽しむ「万年筆用一筆帖」にも生かされている。手漉きはもちろん機械抄きでさえ、和紙は製造の工程によってどうしても表と裏の質感が変わる。紙業界では当たり前であり欠点のようにさえ思われていた特性を、森崎さんは「新しい楽しみ方」として打ち出した。裏に書いたり表に書いたり一冊の一筆箋で2種類の質感が楽しめるので、欠点どころかお得な感じさえしてしまう。
「デザイナーはそもそも、職人さんが持っているものを生かす係。できることを引きあげたり、掘り起こしたりする仕事です。新しいデザインを施すより前に、もっとPRしたいポイントが和紙にはたくさんあります。そういうところからメーカーさんと一緒にやっていくのが永遠のテーマですね」と森崎さんはいい、「やりたいことが多すぎて大変です」と楽しそうに笑った。
森崎さんのデザインが見るものの心を動かすのは、たんなる表層のデザインではなく、ものの本質や有り様にまできちんと迫っているからだろう。そうして生み出されるプロダクトには、美しい紙を使うこと、自分の手で書くことの喜びが満ちているのだ。