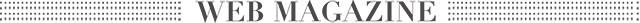紙ノ余白
『樹皮が和紙になる』続:石州和紙
楮(コウゾ)の皮剥ぎ(カワハギ)のお話です。

クリスマスソングがラジオから流れる師走の頃、
落葉した後に刈り取られた楮の束が、紙漉き工房の前に山のように積まれます。

根元の方は、大きくて直径6センチ、幹先の方は1センチ以下になる楮が
大の男性が抱えられるぐらいの束になっています。
一体何が始まるかというと、
これを蒸し上げ、熱いうちに人の手で、皮を剥ぐのです。
この「皮」が和紙になります。


蒸気で熱せられると、木の外皮と芯の間に隙間が生まれ剥ぎやすくなります。
長い時には1週間ほど時間をかけ、一家総出で一気に取り組みます。
大の大人が10人は入る大釜に水を張り、これまた大きな蒸籠を乗せ、楮の束を蒸します。
徐々に、工房の周辺には、さつま芋を蒸したような甘い匂いが立ち込めます。
(余談ですが、三椏(ミツマタ)を蒸した匂いはイチジクの香りですー筆者観)

大きい蒸籠に蒸気の隙間を作りながら束を積む

もくもくと立ち上る蒸気とともにホカホカに温まった楮の束を取り出す
湯気がもくもく上がる束に冷水をかけ、木芯を収縮させ、さらに根元を大きな木槌で打ちたたき、皮を剥きやすくするきっかけを作ります。
そして、大きなござの上に皆で腰を下ろし、片手に原木、片手に皮を持ち、片足を支点に剥いでいきます。

皮と芯に隙間が生まれる

座りながら手足を道具に剥いでいく

大きい蒸籠に蒸気の隙間を作りながら束を積む

もくもくと立ち上る蒸気とともにホカホカに温まった楮の束を取り出す

皮と芯に隙間が生まれる

座りながら手足を道具に剥いでいく
強いて例えるなら、失敗して靴下を脱いだ時のように、皮の内側が外になるように剥ぐ「筒剝ぎ」が、石州の特徴です。
筒剝ぎにすると剥いだ皮に巻き癖がつきにくく、次の処理工程がスムーズになります。

筒剝ぎ
筒剝ぎにした外皮を親指と人差指で持てる量に束ね、
日本海から吹き荒む北風で乾かします。

皮剥ぎ乾燥

皮剥ぎ乾燥・遠景
この、まるで大きな昆布が干されているような光景が石州での年末の景色です。
ひと昔前では、公道での使用許可を取って道沿いの至る所に竹の干し竿を渡して皮干しをしていたと言います。
また、剥いで残る大量の木の芯(または「木がら」と地元の方は呼びます)は、昔は火を炊いて楮を煮たり、紙干しの鉄板を温めていたのでその燃料に使ったり、または地元の方の風呂焚きの薪に重宝されていたそうです。
今は工房の熱源もボイラーに変わり、木がらの引き取り手は年々減っています。

木がら
一通り乾いた皮は、束ねていた部分にも風を通すために、「てねかえ(石見の言葉:束を解き、また束直すこと。髪を結い直すような行為を指す)」て、カラカラになるまで乾燥させ、倉庫にしまいます。
これが、1年分の紙漉きの原料となります。

筒剝ぎ

皮剥ぎ乾燥

皮剥ぎ乾燥・遠景

木がら
私のお世話になっている西田和紙工房では、この作業一連がしまいになると、皆でお善哉を頂く、という習わしがあります。
無事に、一年間紙を漉けて、来年の原料を用意できたことへの感謝と労いのような、このひと時が私はたまらなく好きです。
私も年末には必ず参加させてもらい、もう4回目ほどになりますが、楮の落葉が遅れたり、普通なら日本海の吹き飛ばされそうなほど強い北風があまり吹かずに、雨が続いて剥いだ皮がなかなか乾かず、高い湿気と温度によるカビの予防に悩まされるといった風に年々、気象の変化を感じます。
地元の方は小学生時分から皮剝ぎを手伝うこともあって、工房のおばちゃん達はもう大ベテランです。
お喋りしながら、皮の束をあっという間に作っていく様を見て、毎年足腰鍛えねば、と決意する筆者です。
寒い時期にする作業ではありますが、熱い楮を扱うので、うっすら汗をかきますし、何より皆でワイワイと集まって進めるので、工房には活気があふれます。
大変な重労働ではないのですが、自分なりのリズム感や身体に負担をかけないコツをつかむことがポイントだと思います。
私も60歳を超えてもお手伝いできます様に。
毎年精進です。